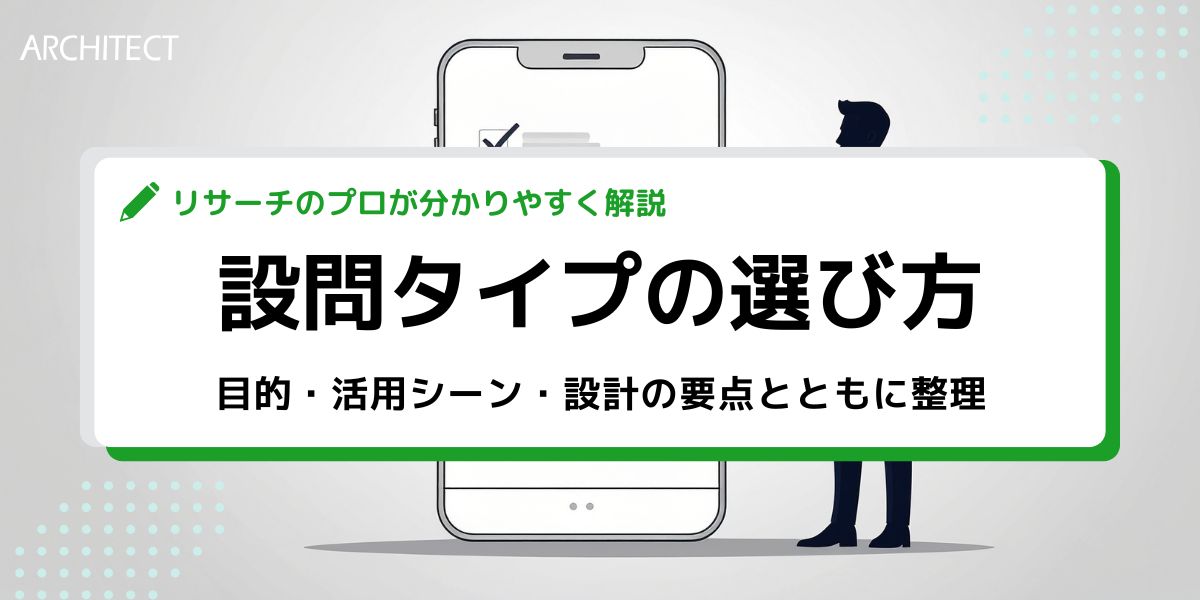設計の早い段階で最も効いてくるのは、実は「設問タイプの選定」です。サンプルサイズや統計手法よりも、まず“何をどの型で聞くか”を間違えると、インサイトは鈍ります。本稿では、主要な設問タイプを目的・活用シーン・設計の要点とともに整理し、後半で生きたケーススタディと、現場で使える設問設計チェックリスト(何を/なぜ/どうやって)を提供します。
設問タイプの基本軸
設問は大きく絶対評価と相対評価に分かれます。
・絶対評価:対象を単体で評価する(例:「この商品の満足度を0〜10点で」)。
→ 市場全体の中での“絶対的な良し悪し”や満足の水準を見るのに向く。
・相対評価:複数対象を比較する(例:「AとBのうち、どちらが好ましいか」)。
→ 選好の序列や、微差の比較検出に強い。
この軸に「何を測るか(好意、意向、知覚、特性、全体評価など)」を掛け合わせると、具体的な設問タイプが決まります。
よく使う設問タイプと実務での使い分け
下記は現場で頻出のタイプと使いどころについて簡単に解説します。
| 好意度評価(好き↔嫌い) | 第一印象や情緒的反応の把握に有効。ただし好意=購入ではないため、必ず意向系とセットで。 |
| 購入意向(買いたいか) | 商機の見込みを直接問う。社会的望ましさのバイアスを受けやすいので、価格や入手容易性など制約条件を明記すると精度が上がる。 |
| 飲用/使用意向 | 食品・飲料・日用品等の“試しやすさ”の指標。購入意向とのギャップが出やすい(試したいが買うとは限らない)。 |
| 知覚評価(強い↔弱い) | 味、香り、色、刺激など特性の輪郭を取る。共通理解のため、アンカー説明(例:「5=一般的な市販コーラ程度の炭酸強度」)を添える。 |
| 特性評価(プロファイリング) | 開発や品質改善の指南役。用語定義を事前に合意してから実施しないと、解釈がばらける。 |
| 点数評価(0–10/100) | 直感的で集計しやすい。個人内の採点基準差を平準化するため、言語ラベルや基準例を併記する。 |
| チップゲーム(配分法) | 重視点の優先度付けに強い。合理的な選好を引き出せる一方で回答負荷が高い。設問数は絞り、要素は互いに独立に。 |
| 全体評価(総合印象) | KPIとして時系列に追いやすい。要素評価とスケール統一が前提。 |
| 相対評価(A vs B) | 差分検出力が高い。比較対象が多い場合はランダム化と比較ペアの設計(近いもの同士を当てる)で負荷とノイズを抑える。 |
調査目的から逆算する設問タイプの選び方──主軸と補助の決め方
意思決定(調査目的)から逆算して、どの設問タイプを主軸・補助で採るかについて解説していきます。「何を決めるための調査か」を先に定め、その意思決定に直結する主軸の設問タイプを1つ置き、解釈と施策設計を支える補助の設問を必要最小限で足します。手順は次の通りです。
ステップ1:意思決定を言語化する
例:「改良版を市場テストに進めるか」「AとBどちらを採用するか」
ステップ2:主KPI(主軸の設問)を1つだけ決める
例:「購入意向」「相対選好」「総合評価」など
ステップ3:ドライバー把握と水準担保のために補助設問を加える
例:「チップ配分」「知覚/特性」「点数評価」
ステップ4:前提条件を設問に固定する
価格・使用文脈・ブランド提示/ブラインドなど
ステップ5:スケールとラベルを統一する
段階数・端点の表現を主軸と合わせる
ステップ6:合否・基準値を事前に決める
例:意向+0.3pt以上、相対選好で60%以上、p<.05 など
以下、代表的な調査目的ごとに「主軸」「補助」「判断の仕方」「設計メモ」を示します。
① 製品の魅力評価
主軸:点数評価または全体評価(絶対水準を見る)
補助:好意度(情緒の入口)
どう読むか:まず“どれくらい良いか”という絶対水準を点数や全体評価で押さえる。そこに好意度を重ねると、情緒→総合の流れが見える
判断:「目標点を超えたか」「競合既存品の基準を満たすか」
設計メモ:点数と全体は同一スケールに。端点ラベルは意味対称に
② 購買可能性の見極め
主軸:購入意向
補助:チップ配分(重視点)、価格納得感・入手容易性
どう読むか:意向を主軸に“買う/買わない”のドライバーを補助で定量化。チップ配分で重視点の優先度、価格納得で制約条件を確認
判断:「意向の閾値(例:5段階で+0.3以上)を満たすか」「重視点の構造が製品特性と整合しているか」
設計メモ:価格前提は設問に明記。社会的望ましさ対策として、可能ならブラインド→ブランド提示の二段測定
③ 味覚・感性分析(開発ブリーフ直結)
主軸:知覚評価(強さ・質感)
補助:特性評価(プロファイル)
どう読むか:狙いの官能プロファイルに対して、属性ごとのギャップを測る。知覚で輪郭、特性で細部を押さえる構え
判断:「目標プロファイルに収束しているか」「ギャップの大きい属性はどこか」
設計メモ:用語定義とアンカー説明を事前合意(例:「5=一般的な市販コーラ程度の炭酸」)
④ コンセプト/パッケージ比較
主軸:相対評価(A vs B)
補助:点数評価(絶対水準)
どう読むか:まず相対の優位性(どちらが好ましいか)を主軸で取り、次に絶対水準の担保(“どちらも低水準”を除外)を点数で確認
判断:「相対で優位(例:選好率60%超)かつ点数が合格基準を下回らないこと」。
設計メモ:比較対象が多いときはランダム化と比較ペア設計で負荷とノイズを抑える。
⑤ ブランド印象・広告効果
主軸:好意度(態度変容の入口)
補助:全体評価(最終印象の出口)
どう読むか:露出前後で好意の変化を見つつ、総合への波及を全体評価で確認します。入口(好意)→出口(総合)が整合しているかがポイント
判断:「好意の上昇」「全体評価の上昇」「効果量(例:d≥0.3)」を串刺しで。
設計メモ:刺激の提示順・文脈を固定。スプリットサンプルで創造物ごとの純増を分離。
よくあるつまずきと回避策(共通)
・主軸と補助の逆転:比較評価で点数だけを見ると微差を落とす。相対で差を見る→点数で足切りの順。
・好意=購入の取り違え:好意をKPIにしない。意向や行動代理を主に据える。
・前提条件の曖昧さ:価格・利用シーンを設問に書き込む。条件が揺れると解釈が崩れる。
・スケール混在:段階数・端点ラベルは主軸に合わせて統一。
【ケーススタディ】新飲料商品テスト──“結果をどう活かすか”
背景と設計
機能性飲料の新商品プロトタイプを、N=400(対象者均衡配分)でテスト。設問構成は、知覚評価(味の濃さ・炭酸・後味など7段階)、好意度(味・パッケージ5段階)、飲用意向(5段階)、チップゲーム(重視点100点配分)。狙いは三つ:(1) 総合印象と意向の水準把握、(2) 意向のドライバー特定、(3) 改善のレバーと優先順位の確定。
主要結果(要約)
・飲用意向の平均は3.2/5。総合印象は6.8/10で、「印象は悪くないが“試したい”まで届いていない」状態。
・相関では**味の濃さ(r=-0.41)と後味の重さ(r=-0.36)**が意向を下げる方向。
・重回帰(標準化β、VIF<3で良好):味の濃さ β=-0.35、後味 β=-0.24、価格納得感 β=+0.22、パッケージ好意 β=+0.11。
・チップゲームでは「スッキリ感」が最重要(配分の28%)。現状の知覚平均は「やや重い」側に偏り。
“どう活かすか”を数式で決める(優先度の定量化)
改善の優先度は、影響度 × 改善余地で見積もります。
ここでは影響度=標準化β、改善余地=(目標水準 − 現状平均)と定義。
例)味の濃さ:β=-0.35、現状平均=5.2/7、目標=4.5/7(“やや軽め”)
→ 改善余地=-0.7(軽くする方向)、潜在インパクト=0.35×0.7=0.245
例)後味:β=-0.24、現状=4.9/7、目標=4.3/7
→ 潜在インパクト=0.24×0.6=0.144
結論として、味の軽量化が最優先、後味調整が次点。価格納得感の向上(訴求メッセージ再設計)も有効だが、製品側の物性改善が先。
施策設計(リサーチ→開発→検証の接続)
ステップ1:開発ブリーフ:
「スッキリ感」をKPI化(“後味の軽さ”5.0→5.5を目標)。味の濃さは5.2→4.5にチューニング。
ステップ2:試作とマイクロテスト(n=80×2セル、対照=現行プロト):
主要評価=飲用意向、知覚2属性(味の濃さ・後味)、副指標=価格納得感・パッケージ好意。A/Bブラインド→ブランド提示の順でバイアス確認。
ステップ3:成功判定基準(ゲート)
飲用意向:+0.3pt以上の上昇(5段階)
知覚:味の濃さ -0.6以上の改善、後味 -0.4以上
有意性:p<.05、効果量 d≥0.3 を目安に
ステップ4:市場投入判断
ゲート達成+価格納得感に悪化がないこと(βの正方向ドライバーを毀損しない)
再テストでの確認ポイント
・効き筋の再現:回帰の符号と大きさが維持されているか。
・副作用:味を軽くした結果、満足度が下がっていないか(好意度・総合評価のチェック)。
・需要へのつながり:飲用意向が購入意向に波及しているか(ギャップ縮小)。
要するに、“結果をどう活かすか”は「ドライバー特定 → 改善余地の定量化 → 成功基準の明文化 → 小さく検証」で一本道にする。ここまで書き切ると、組織は動きやすくなります。
【実務向け】設問設計チェックリスト
調査目的と設問タイプの適合
・何を:意思決定(例:改良A/Bの選定、価格帯の確定)に必要なアウトプット。
・なぜ:目的に合わない設問は、解釈不能な“数字”を生む。
・どうやって:調査計画の冒頭に**「意思決定テーブル」**を作る。
例)「飲用意向が+0.3以上で開発継続/未満で再配合」
→ その判定に必要な設問(意向・知覚・価格納得感)を逆算で確定。
絶対評価と相対評価の併用
・何を:絶対水準と相対優位の双方。
・なぜ:A>Bでも、両方悪い可能性がある。
・どうやって:点数評価(絶対)+相対選好を同一対象で設計。分析では「相対差」と「閾値超え率(例:7点以上の割合)」を併記。
回答者負荷の管理
・何を:設問数・ページ数・1ページあたりの設問密度。
・なぜ:負荷増は直線回答・離脱率増に直結。
・どうやって:1ページ5〜7問程度に収める。長文は分割。平均完了時間の予備テスト(n≈20)で速度異常者の閾値(下位5%)を設定。
スケールの一貫性
・何を:段階数、端点ラベル、中点の扱い。
・なぜ:混在は回帰や比較の解釈を難しくする。
・どうやって:全設問で段階数を統一(例:5段階 or 0–10)。端点ラベルは意味対称に。総合評価と要素評価は必ず同一スケール。
好意・意向・行動(の代理)の分離
・何を:好意(好き)、意向(やりたい/買いたい)、行動(購入・試用の予兆)。
・なぜ:混在させると因果の経路が判別できない。
・どうやって:3者を別設問で取得。行動代理には「購買確率自己評価(%)」「次回購入予定のブランド」なども併用。
バイアス対策
・何を:社会的望ましさ、順序効果、アンカリング。
・なぜ:意向が過大評価されやすい。
・どうやって:ブランドブラインド→提示の順で二段測定。選択肢・刺激のランダム化。価格前提示での意向は価格条件を明示。
品質管理(データクレンジング)
・何を:スピーダー、直線回答、注意テスト、オープン回答の質。
・なぜ:ノイズは効果量を縮め、偽陰性を招く。
・どうやって:注意チェックを1〜2問。完了時間の下位●%を除外候補に。反応の分散が極端に小さいケースをフラグ。
多重共線性と非線形の確認
・何を:VIF、二次項・交互作用の必要性。
・なぜ:係数の不安定化や誤った符号のリスク。
・どうやって:VIF < 5を目安。超過要素は統合または削除。曲線が想定される要素は二次項を追加、またはツリーモデルで補完。
サンプル計画と合否ライン
・何を:セルサイズ、検出力(power)、成功基準。
・なぜ:効果の見落とし(βエラー)を防ぐ。
・どうやって:主要指標の最小検出差(例:意向+0.3)から事前パワー設計。成功基準(ゲート)を調査前に明文化。
設問タイプ選定フロー(現場用メモ)
意思決定は何か?
・量的な合否/閾値がある → 絶対評価(点数・意向)を主軸に
└─ 競合や代替案も比較する → 相対評価を併設
・ 序列・微差の比較が主目的 → 相対評価を主軸に
└─ ただし絶対水準の担保に点数評価を併設
まとめ:設問タイプは“分析の前”に勝負が決まる
・設問タイプは意思決定から逆算して選ぶ。
・絶対と相対は補完関係。両輪で水準と優位を押さえる。
・結果は影響度×改善余地で“どこをどれだけ直すか”に落とす。
・チェックは「何を/なぜ/どうやって」で運用できる言葉にする。
ここまで設計できていれば、集まったデータは“単なる数値”ではなく、動くための根拠になります。
 リサーチサービス
リサーチサービス リサーチBPO
リサーチBPO タレントパワーランキング
タレントパワーランキング イベント動員
イベント動員 リサーチ関係のご相談・お見積
リサーチ関係のご相談・お見積 タレントマネジメントについて
タレントマネジメントについて その他お問い合わせ
その他お問い合わせ